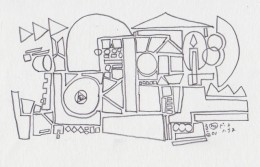淡海宇宙誌 XXXXIV 壊すをつくる
昨年末に家を買いました。
新居は…と言っても明治の十三年に建てられた古民家で、これから少し改修をして、桜の頃には引越しをする予定です。
「一国一城の主」という言葉もありますが、みんなの家になればいいなと思います。
僕自身は井の中の小さな蛙なのだけれど、びわ湖はとても広くて深い井戸なので、日本国中・世界と直につながっている。それで素敵な人たちがひょっこりのぞきに来てくれる。そんなお客をゆっくり迎えて、時には小さな集いもできる。そういう基地が必要だったし、そういう家にしたいと思う。
でそのために、暮れから正月返上で建築以来百三十三年間の家の歴史の「物証」たちとの格闘でした。家と一緒に一切合切引き受けた家具や調度や物品全部を明るみに出し、不要のものを仕分けして、引き取り先に手渡して。
ある友人は古い畳が何十枚も入用とかで、そっくり持っていくのです。これから建てるお家の壁の素材に使いたいらしい。
旅立つ畳を見送りながら、改めて昔の家の感心なのは、そのうち家が「解散」しても、部材や素材にその後の進路があるらしいこと。家の建て方だけでなくきちんと壊すその壊し方も同じくらいに大切で、つまり「壊すがちゃんとつくられている」らしいこと。
思い出します。二十年前、地球の未来を憂えるひとりの少女が「直し方のわからないものを壊すのはやめて下さい」と世界に向けて訴えた(※)。
けれど未だに壊し続けて、その上で「壊し方のわからないもの」もたくさんつくってしまったなあ。そんな話をしようかな。
大人になった彼女が2月のお客です。
※1992年、当時12歳の少女セヴァン・カリス=スズキがブラジル、リオ・デ・ジャネイロで開かれていた地球サミットでスピーチした。大人となり、母になった彼女が2月に滋賀にやってくる。