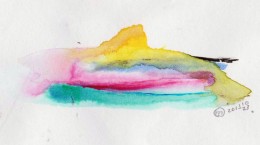淡海宇宙誌 ⅩⅩⅩⅩⅠ 秋がもったいない
雪崩に呑まれて、いよいよ死というものに直面した瞬間におもい浮かべたのは、ほんとうにささやかな日常の、なにげない風景でした。たとえば朝、洗面台で顔を洗っているわが子の、その後ろ姿の、つま先立ちしている、そのかわいらしいつま先。そういうものがありありと目に浮かぶ――。
たしかそんなようなことを、ある有名なアルピニストが話しているのをテレビで見て、ふかくなっとくしました。
というのも、詩人のまなざしというのはそういうところにあるのではないか、ということを、ちょうどこのごろ考えていたからです。
あかいところだけのこして
きえかけていたにじ
ぐみの葉に
とまっていたかたつむり
はっきりと
おぼえている
しかられて
背戸のはたけに
でていたとき
とか、
わらのかげにかくれた
ことしのいなわらだ
秋の日よりのにおいがする
鬼だ
ぞうりの音が
近づいた
行きすぎた
すぐあとに
みそさざいがきて
しっぽを
ちょっ ちょっ とやっている
というような詩は、死の方角、「まつごのまなざし」から見た世界の静けさ美しさだと思えるのです。
じぶんの死に目に浮かぶ景色がこんなのだったら、いいなというのも変ですが、そうならやっぱりいいなと思う。
思いがけないあの死に目にもそんな静かな美しい景色が映っていたのであって欲しいな。
いのりとともに、秋がやっぱりうつくしいので、見えるもの見えるもののぜんぶが、もったいなくて、もったいなくて。
引用
「にじとかたつむり」「かくれんぼ」木下夕爾 『木下夕爾児童詩集 ひばりのす』 1998年、光書房